

Liberty Audioから出ているLaudを購入しました。
ソフトウエア自身は$350程度でしたが、DSPの載ったサウンドボードが別途必要でこちらは約$250でした(送料、税抜き。込みで約36000円)。さらに校正データ付きマイク($150程度)を含め、全部で9万弱かかったことになります。
現在入手可能なスピーカ計測機器のなかでは標準的な価格といえます。他に、LMS(LinearXの製品で日本ではレイオーディオが代理店をやっています。約$1500)やCLIO(イタリアのAudiomaticaが販売、まだ日本にはディーラーがないが、
ORCAがUSでは代理店をやっています。こちらはフルセットで$895で最近はLiteが登場しこちらはマイク付きで$599(編集注1)とお買い得。ただし、そのうちUp
Gradeしたくなり、結局$895払うことになる)があります。Liberty Audioはかつてパラレルポートにつなぐタイプの計測機器IMPをキットとしてSpeaker
Builder誌に載せており、低価格で大いに受けたようです。後にこのIMPは最大周期長系列
(MLS)を使用したQAMを可能にさせるための亀の子基盤を発売し、アマチュア測定機具史上最高にして最安のものとなりました。IMPの発表から3年ほどで、
Laudの発売となります。当時PSAと呼ばれるDSP付きのボードの使用を前提にソフトウエアは書かれ、半田ごての不得意なSpeaker
Builderにとっては失敗なく低価格で購入できる(ボード込みで$600程度だったと記憶している)測定機械としてデビューしました。現在ではTurtle
BeachのFijiあるいはPinacleを標準として、PSAタイプのDSP付きサウンドボードをサポートしつつ、進化を遂げver3.1となっています。Laudは主に二つの測定を行います。一つはスピーカの測定であり、もう一つはアンプ等の測定です。スピーカ測定は
Gated Sine Wave(GSW)によるQAMとMLSによるQAMの測定、インピーダンス測定、ひずみ率測定があります。
編集者注1:LAud/LspCADをLiverty Instrumentから/CLIO&SoundEasyをORCA Designからイーディオでも求めました。LAudは既に日常の測定器具として利用しています。ただしここにあるTurtle BeachのボードがDisconなので、CLIOを最近求めました。ところがCLIOはDOSのConventional Memoryを580Kbyteのフリーエリアが必要です。日本語環境では測定は無理のような気もします。再度チャレンジしてみます。
MLSを用いたQAM
MLSはある段数のシフトレジスタから生成される2値系列の中で最も周期の長い系列です。
シフトレジスタの段数をmとすると周期Lは2の(m-1)乗となります。
MLSの特徴はその自己相関特性にあります。MLSの自己相関特性は周期Lで正規化した場合、位相差0で1、その他では−1/Lとなります。
白色雑音の自己相関関数がディラックのδ関数になることを思い出していただけば、MLSは白色雑音に近い周波数スペクトルを持つことがわかります。しかしながらMLSは完全な白色雑音ではありません。これは周期を持っているからです。一般にこれらの雑音は疑似雑音(PseudNoise:PN)と呼ばれます。この疑似という単語は正確にはランダムでなく、確定的すなわち、いつでも同じランダムなものを生成することができるという意味も含んでいます。CDや各種音源ソフトで用いられている雑音の音源、雑音源にはこのMLSを用いていることがしばしばあります。確定的なランダム系列であるため、DAコンバータの直線性を補正するために用いられるディザという技術は、デジタル段でこのMLSを加え、DA変換した後アナログ段で同じ雑音を抜くという作業をしています。
さて、実はMLSによるQAMはその雑音特性を用いているわけではありません。
実際には、MLSの時間的な性質すなわち、自己相関特性の鋭さを用いています。ではどのようにQAMを行っているか順を追って説明します。まず、測定したいもの
(Device Under Test:DUT)にMLSを入力し、その応答を記録します。この時点でDUT
にとっては疑似雑音系列が入力されることとなります。
DUTのMLS応答からその先頭を探し出します(一般的には同期補足:Synchronization
Acquisitionとよばれます)。これを行うには、応答時系列に1単位時間ずつずらしたMLSをかけあわせて和をとる(すなわち畳み込み)を行い、その最大値が検出される時点を同期点とみなします。(編集注2)
次に、同期点からMLSの周期時間分の応答を切り出します。切り出された時系列は更にMLSとの畳み込みを行います。畳み込みは、入力された系列にある時間遅らせた系列を掛け合わせたものを掛けあわせ積分を行うことによって行われます。この作業により、MLS応答がインパルス応答に変わります。
Laudではこの畳み込み(正確には離散畳み込み)の高速化手法として、高速アダマール変換(Fast
Hadamard Transform:FHT)を用いています(FHTは本来、Walsh関数系を用いた直交変換の高速アルゴリズムですが、
Walsh関数系から構成される直交行列、Sylvester型Hadamrd行列は行と列の基本変形により、MLSのシフトから構成される正方行列を心行列に持つM系列型Hadamard行列に変形できることが知られていますので、若干のデータの入れ替えにより、このようなMLS応答の畳み込みをFHTで行うことができます)。
MLS応答からインパルス応答を生成するメリットは、MLSとの畳み込みを行う際のMLSとの乗算過程により、MLSと相関のない成分はそのスペクトルがMLSの周期倍の領域にまで拡散され、MLSと相関のある成分は逆に低周波領域に逆拡散されます。積分は周波数領域で見れば低域通過フィルタなので、MLSと相関のある成分のみが出力に現われ、他の成分は阻止されます。
したがって、S/N比が飛躍的に向上します。もちろん、計算量が大幅に増加しますので、速度の点では喜んでもいられないのですが、
44.1kHz標本化、16bit量子化のデータを33MipsのDSPでも充分実用になる速度です。
次にMLS応答から生成されたインパルス応答から、反射波の影響と思われる部分を除去します。ここは仕様書に書いていないので、厳密にどのようなアルゴリズムで反射波を分離しているか定かではありませんが、おそらく、インパルス応答の崩落線をみて、一旦負になったその微係数が再び正になっている点を判断している程度だと思います。ここから先のデータはすべて0と判断し、インパルス応答の先頭からフーリエ変換を施し周波数領域に変換します。窓はいくつか用意されていますが、主にBlackmanの右半平面のみを用いるHalf
Blackmanが推奨されています。インパルスレスポンスはスピーカが計測対象の場合、左側に応答があることは考えられませんので、右半平面のみの窓が適していると書いてあります。そして、反射波の影響を無視できる、疑似無響室計測が完成します。
しかし、ここで大きな問題があります。それは、所詮疑似で何かが欠けているわけです。それは低域特性です。時間領域と周波数領域の積ΔtΔωは1/2以上という不確定性原理が成り立ちます。不確定性原理はその下限を示したに過ぎません。フーリエ変換ももちろんこの制約を受けます。したがって、低い周波数までみたい場合は測定時間を長く取る必要があるわけです。しかし、反射の影響を取り除くために、時間領域は大きな制限を受けていますから、低い周波数は観測できません。実際には、天井あるいは床からの反射が最も早くマイクに到達するため、せいぜい3mくらいの距離を音波が進む時間、すなわちほぼ 10msくらいしか観測できませんので、低域測定限界は数100Hzのオーダーです。しかし、今まで定在波の影響によるピークやディップで見えなかった色々な反射が見えてきます。(編集注3)
編集注2: LAudの開発元であるLiberty
Instrumentに確認したところによればこの畳み込み積分で先頭を探したりする同期の処理にDSPの能力を生かしているそうです。画面で見るFFTなどはPCの演算能力をそのまま利用しているとのことでした。したがって画面でのFFT(Transform→Fast
Fouririe Transform)などはCPUが高速化すればそれだけ速くなるようです。
編集注3: もともと無響室、あるいはそれに近い反射の少ない部屋ではもちろん低域までのデータが取れます。ただし、スタンドや大きなスピーカでは自分自身が反射・回折を起こすこともあります。無響室に近い低ノイズでの環境ではQuasi
- Anechoic Measurementではなく、LAudのInRoom測定(居室測定)で低域まで取るのが良い様です。この場合には時間窓を長く設定(171mS/6Hz分解能)しています。この時は171mS内の部屋の反射・残響も計測対象となります。
マンガーユニットを使って幾つか測定をしてみました。
マンガーユニットは内部損失の高い高分子フィルムを振動板に用いて、それをリング状に配置されたマグネットで駆動するユニークなユニットです。
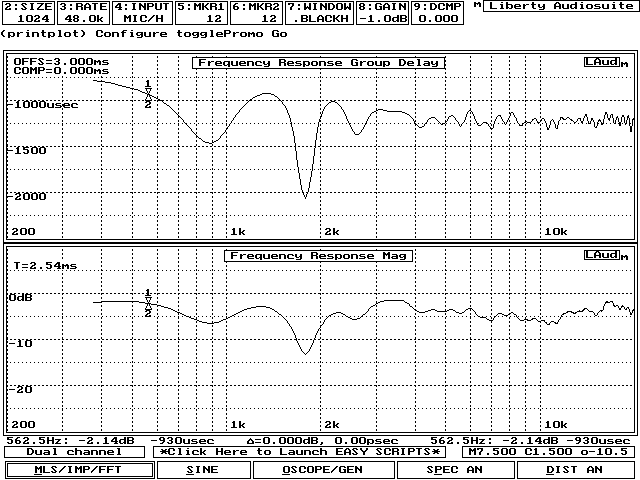
上の図は上半分は群遅延、下半分はQAMのF特です。1k付近のディップとピークはバッフル端反射である事が幾つかのシミュレーションソフトで確認されています。バッフルサイズは30x36(wxh)です。
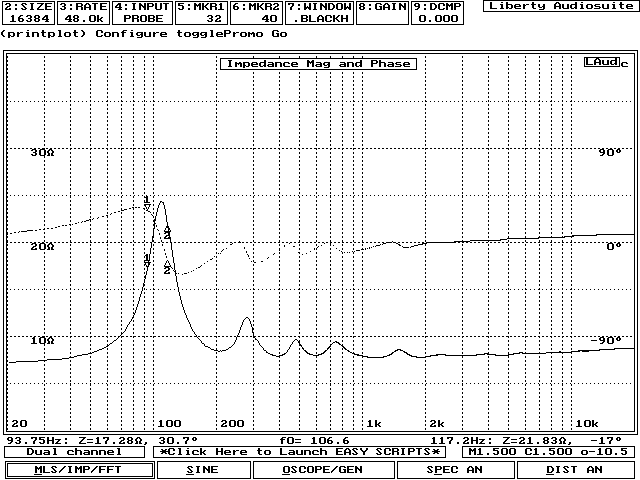
上の図はMangerユニット8Ω版(W05,2.1.1.16/16Ωボイスコイル並列)インピーダンス特性です。中域の反射は原因が良く分かっていません。
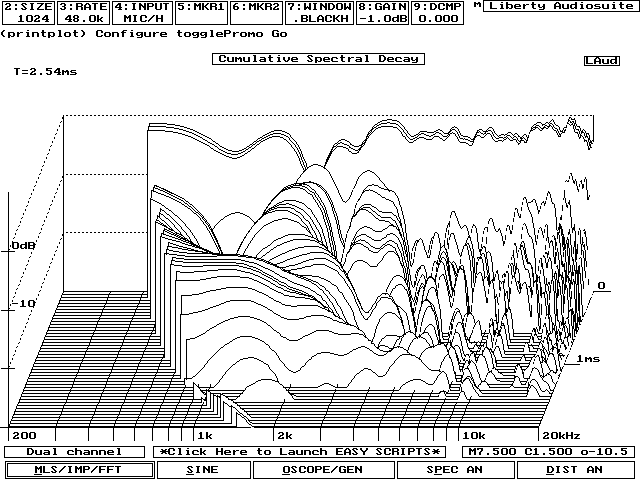
Cumulative Spectral Decay(CSDあるいはWaterfall)です。ユニットや箱の持つ共振の一部を検出する測定手段です。
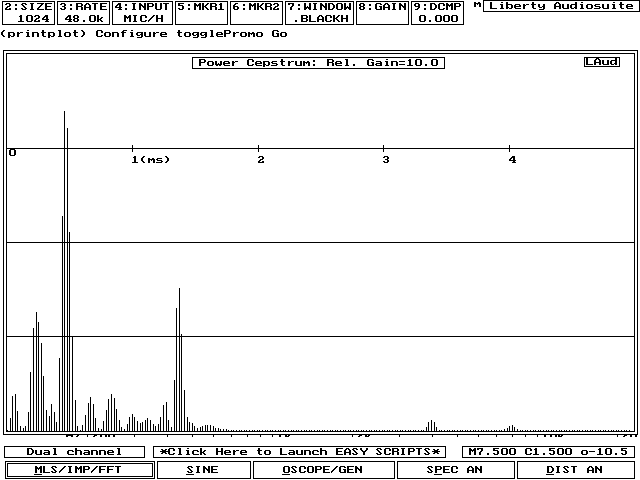
ケプストラムもついでに測ってみました。
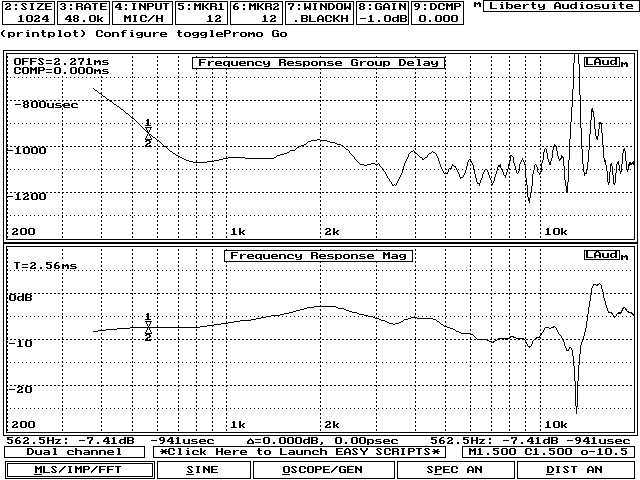
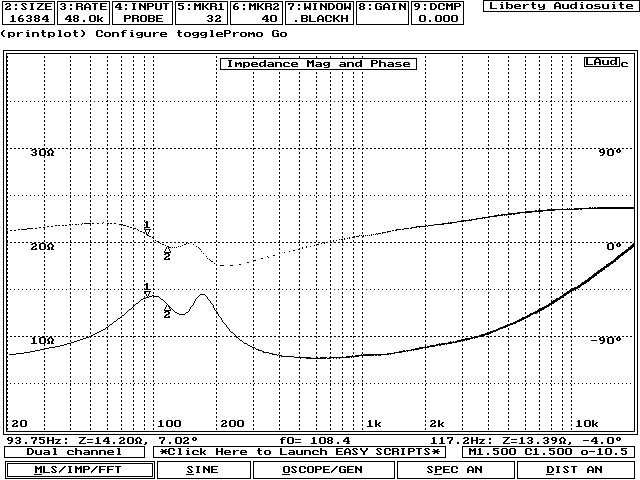
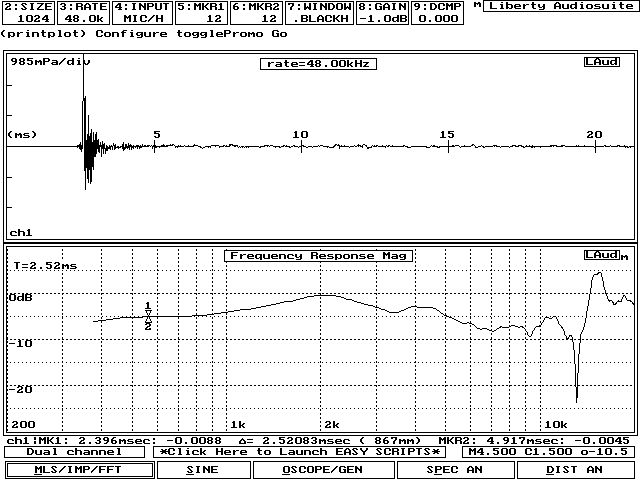
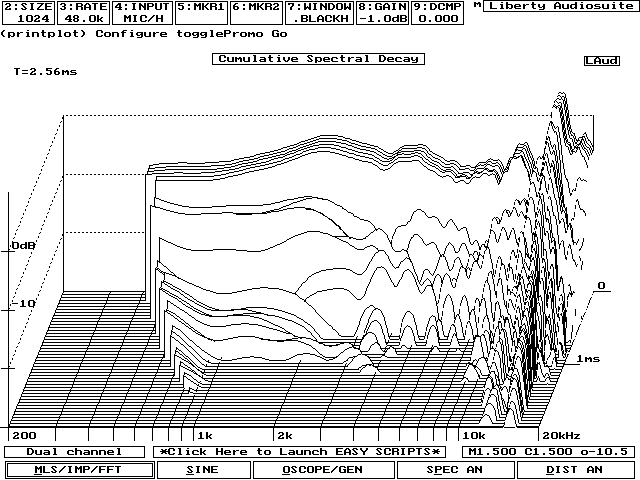
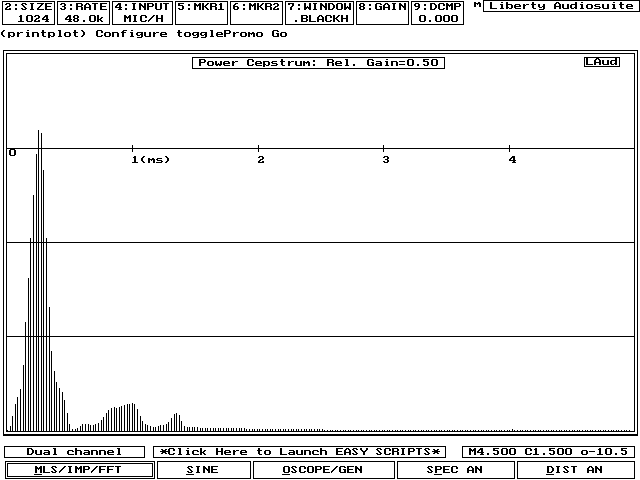
nisinaga@crl.go.jp